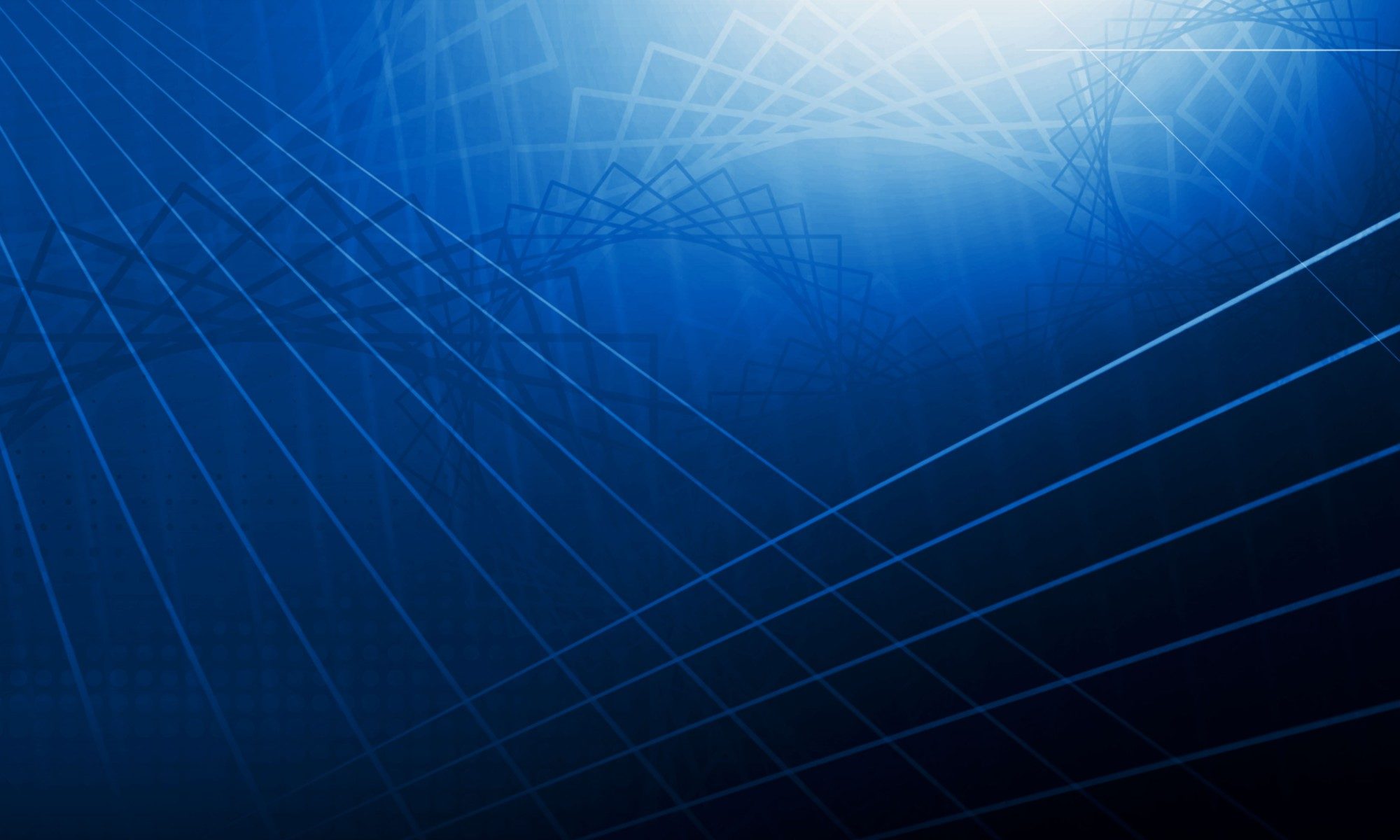ここでは、日常会話で使える知的な小話と、実際の使用例を紹介します。
モラルハザードとは
モラルハザードとは、元は保険業界で使われていた用語で、被保険者が保険に入ったことによりリスク回避や注意義務を怠るようになってしまう現象を指します。
例えば、自動車保険に入ったことにより、事故を起こしても保険金が貰えることから、以前より運転が荒くなり、逆に事故の確率が上がってしまうような場合、モラルハザードが発生していると言えます。
また、健康保険についても同様のことが起きえます。
日本には国民皆保険制度があり、基本的に全ての国民は、3割の医療費を自己負担することで、医療機関で診療を受けることができます。
皆保険は、お金が無い人も治療を受けやすくなる素晴らしい制度です。
しかしその一方で、モラルハザードによって、保険が無い場合と比べて、健康に気を遣う人が減ってしまうのではないかという懸念もあります。
モラルハザードが働くと、自己負担額が安ければ安いほど、「病気になっても安く治せるからいいや」と国民が健康を気にしなくなり、病気や怪我をしやすくなります。
国民健康保険の自己負担がゼロではなく3割なのも、ある程度国民に自費で負担させることで、こうしたモラルハザードを回避させるためなのかもしれません。
事故や病気を防ぐための制度によって、事故や病気が引き起こされるのは皮肉なものですね。
モラルハザードの誤用
モラルハザードは上記の説明の通り、保険に加入したことにより、事故や病気のリスクが増加してしまうという現象のことを指します。
しかし、モラルハザード(moral hazard)の英語の意味を「道徳の危機」と誤って直訳したことから、「道徳の危機」や「倫理観の欠如」といった意味で使われることがあります。
例えば、青少年による凶悪犯罪が起きた際に、若者の道徳観が失われているという文脈で「これはモラルハザードが生んだ悲劇だ」と言われることがありますが、これは本来のモラルハザードの使い方ではありません。
現在はこうした誤用も広まっているので、一概に間違いだとは言えませんが、元の意味とは離れた誤った使い方だと考える人もいるため、注意が必要です。
日常会話での使用方法
「どうせニートになっても生活保護で生きられるからいいや」
「こいつ、モラルハザードが生んだ化け物だな」
本サイトで紹介している用語一覧は以下です。